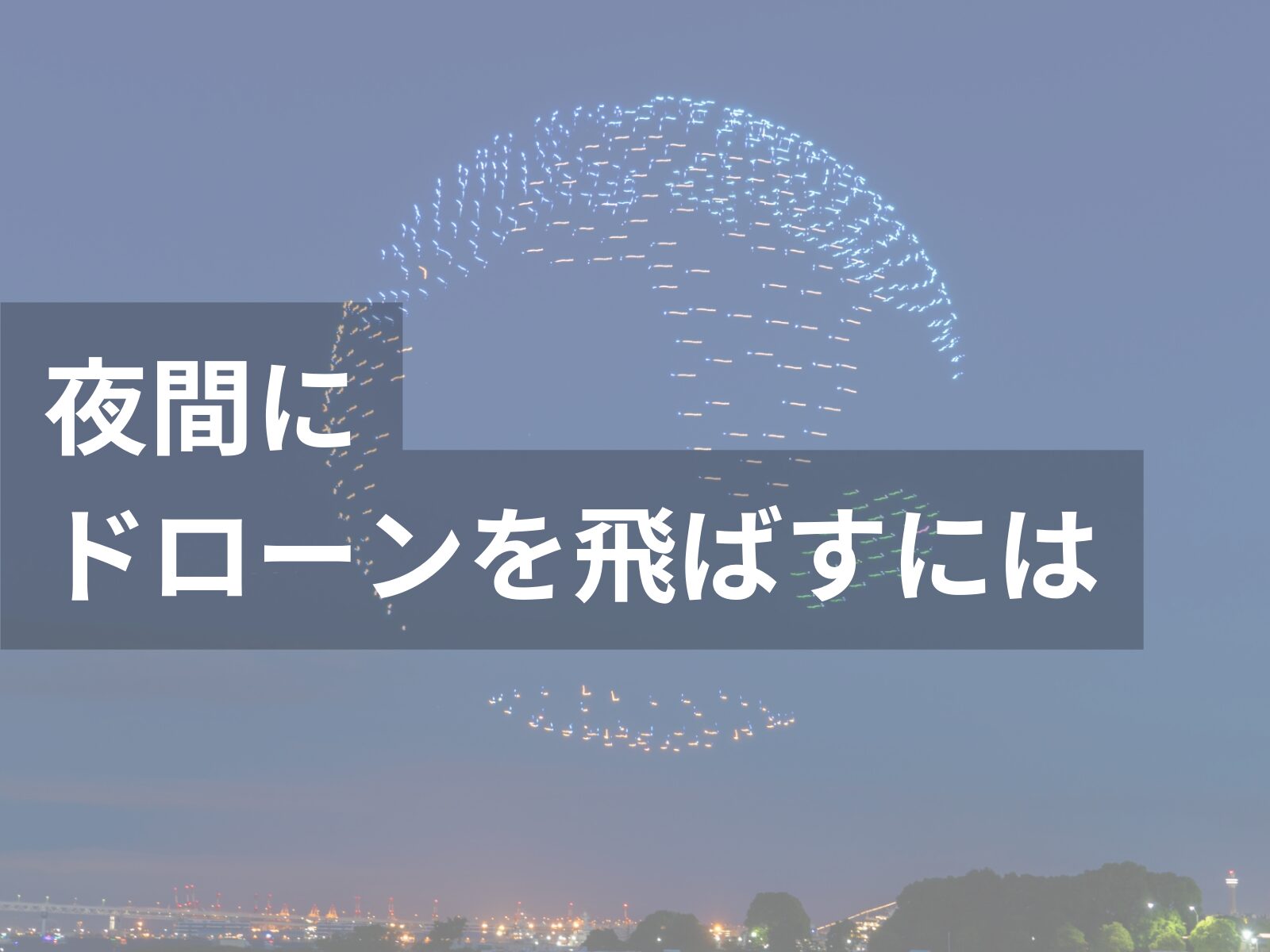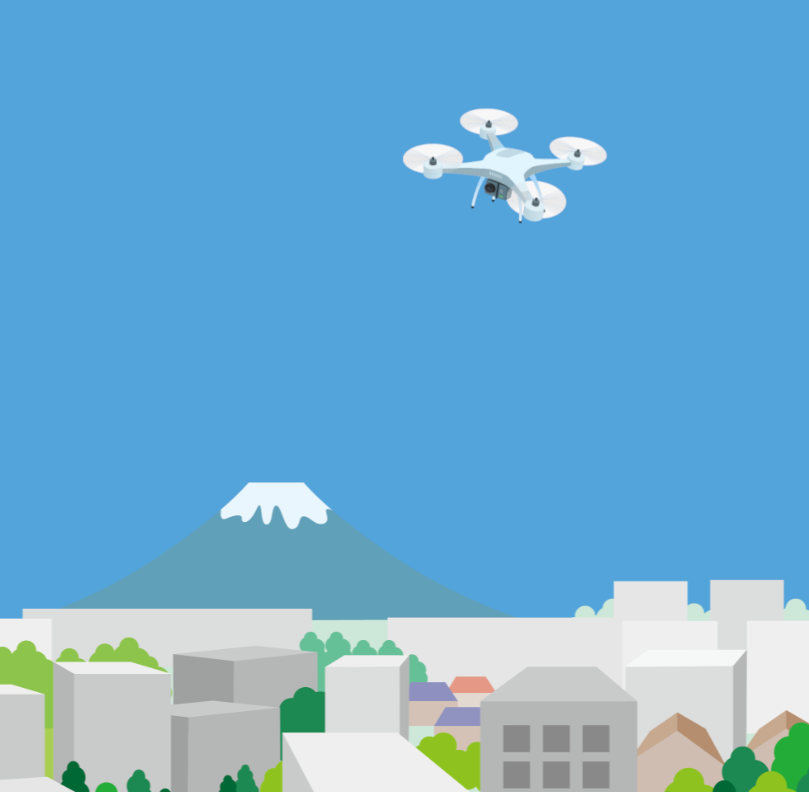『特定飛行とはなんですか – 規制の対象となる空域』では特定飛行のうち航空法の規制の対象となる「空域」についてお伝えしました。
今回の記事ではもうひとつの規制の対象「飛行の方法」について解説していきます。
規制の対象となる6つの飛行の方法
空港周辺や人口集中地区などの規制の対象となる空域以外なら、どのような方法でドローンを飛ばしてもいいというわけではありません。
状況によっては、操縦者に高い技能が求められたり、機体に特別な機能や装置が必要になったりします。このような知識をもたずにドローンを飛ばせば、人やものに被害を与えかねません。こうした危険を防ぐために、空域にかかわらず以下の6つの「飛行の方法」に規制が設けられています。
次の3つの方法でドローンを飛ばす際には、操縦ライセンスを取得して機体認証を受けた機体を使うか、航空局の許可を受ける必要があります。
- 夜間での飛行
- 目視外での飛行
- 人または物件との距離が30メートル以上保てない状態での飛行
また、次の3つについては、操縦ライセンスの有無にかかわらず、航空局の許可を受けなければなりません。
- イベント上空での飛行
- 危険物の輸送を行う飛行
- 物件の投下を行う飛行
なお、航空法では規制されている空域について飛行を認めることを「許可」と、飛行の方法については「承認」とそれぞれ呼びますが、一般にはどちらも「許可」と表しています。このブログでもすべて「許可」に統一します。
先に挙げた6つの「飛行の方法」を詳しく見ていきましょう。
場所や季節によって変わる夜間の時間
ドローンを安全に飛行させるには、ドローンの位置や周囲の状況をつねに目視で監視する必要があります。ところが、明るい日中に比べて、夜間の暗闇では機体を見失いやすく、衝突や墜落などの事故も起こりやすくなります。このような危険を防ぐために夜間にドローンを飛行させることが規制されているのです。
「夜間」とは、国立天文台が発表する「日の入りから日の出まで」を指します。このあいだは、何時から何時までと決められているのではなく、飛行させる場所や時期によって変化します。たとえば、夜間の時間は1年のうちで冬至の日が最長で、夏至の日が最短になります。また同じ日でも東京と大阪では日の入りの時刻が15分ほど違ってきます。
気づかないうちに夜間になってこの規制に違反することがないよう、ドローンを飛ばす際はかならず日の入りの時刻を確認しておきましょう。飛行の時間が少しでも夜間に入りそうなら、あらかじめ許可を受けておくことも考慮してください。時刻は国立天文台のウェブサイトで確認できます。
モニターを見ながらの飛行も目視外
先で述べたように、ドローンの飛行では機体と周囲の状況をつねに監視するのが原則です。監視は目視で行う必要があり、それ以外の方法は「目視外」として規制されています。
ここでの目視とは「操縦者」が「肉眼」でドローンを見ている状態を指します。
補助者がドローンを見て状況を把握していても、操縦者が自分の目でドローンを見ていなければ目視外になります。このような飛行の方法は難度が高く、危険も高まります。
また、双眼鏡を使ったり、ドローンのカメラから送られてくる映像を手元のモニターで確認したりしながら操縦する場合は、肉眼で見ていることにならず目視外になります。視野が限定されてまわりの状況の把握が難しくなり、目視と同じレベルの監視ができないためです。操縦者がメガネやコンタクトレンズをつけてドローンを見ている場合は問題ありません。
操縦者とドローンの距離が何メートル離れていると目視外になると決まっているわけではありません。また、操縦者の視力や天候、ドローンの色と背景との関係などさまざまな条件によってドローンの見え方は変わってきます。目視外、すなわち「自分の肉眼で捉えられなくなる」可能性がある場合は許可の取得を考えておきましょう。
「ひともの30メートル」の意味を理解しよう!
接触や衝突などの事故を防ぐために、ドローンの飛行には「人または物件との距離を30メートル保つ」という規制が設けられています。
このうちの「人」は、ドローンの飛行に直接にも間接にも関わっていない「第三者」を指します。ドローンの操縦者や飛行を監視する人、撮影のスタッフなどの関係者はここには含まれません。
「物件」もこの解釈と同様に、関係者ではない「第三者」の管理する建物や構造物だと考えてください。管理者の依頼や了承を受けている場合は、この物件にはあたりません。
また、樹木や雑草などの自然物と土地は物件には含まれません。舗装された道路や鉄道の線路なども土地の一部と考えます。しかし、それ以外の人工物は、建物であれ、車であれほとんどのものが物件にあたります。
とくに、都市か地方かに関わらず、電柱や電線、信号機、街灯などには注意が必要です。どれも人が生活する場所のいたるところにあり、30メートル以上の距離を保てない場合は、操縦ライセンスや許可を受けなければならないからです。
飛行が禁止されている「イベント」の定義
お祭りや縁日など、多くの人が集まるイベント上空でのドローンの飛行は、原則として禁止されています。操縦ミスや故障などでドローンを落下させてしまった場合、人に対する被害が大きくなるためです。
ただ人がたくさん集まっていればイベントになるわけではありません。飛行が禁止されるかどうかは、
- 特定の場所で開催されるのか。
- 特定の日時に開催されるのか。
- 集まる人数、規模はどの程度なのか。
がおもな基準となります。ただし、これ以外にも主催者の意図を含めたさまざまな観点から、個別の状況に応じて判断されることになります。
イベントにあたる例としては、先のお祭りや縁日のほか、屋外でのコンサート、スポーツ大会、展示会などが挙げられます。信号待ちでたまたまできた人の集まりや、ラッシュ時の人混みなどはイベントにはあたりません。
また、集まる人は不特定多数を指します。たとえば、観客として誰でも自由に出入りできるような運動会はイベントにあたります。しかし、同じ運動会でも、入り口を施錠して観客を入れずに教師と生徒だけで開催する場合のように、入場者のすべてが特定できていればイベントにはあたらないと考えられます。
イベント上空を飛行させる場合にはライセンスの有無に関係なく、日時と飛行の経路を特定した許可申請が必要になります。
許可が必要な危険物の内容
火薬類や高圧ガス、可燃性の物質、有毒な物質などの危険物をドローンで輸送することは原則として禁止されています。輸送中に危険物を飛散させてしまったり、ドローンの墜落により爆発が起こったりするなど、人や物への被害が発生するおそれがあるためです。
ただし、ドローンを飛行させるために必要なバッテリーや燃料は、輸送していることにはならず、危険物には含まれません。
危険物を輸送するためには許可を取得する必要があります。最近では、ドローンを使って農薬の散布を行うことが増えています。この農薬も危険物の輸送にあたります。
固体だけでなく液体も物件の投下にあたる
ドローンを飛行中に物件を投下することは原則として禁止されています。投下した物件によって人や物に被害を与えたり、投下によりバランスを崩したドローンを制御ができずに墜落させてしまったりするおそれがあるからです。
投下が禁止される「物件」には、固体だけでなく水や農薬などの液体も含まれます。
また「投下」とは上空から落とすことをいい、ドローンで輸送した物件を「置く」ことは含まれません。
ドローンから物件を投下する際は許可を取得する必要があります。先に挙げた農薬の散布は「物件の投下」にも該当します。つまりドローンで農薬の散布を行うには「危険物の輸送」と「物件の投下」両方についての許可を取得する必要があるということです。
まとめ
特定飛行に含まれる6つの飛行の方法は、空港周辺や人口集中地区などの空域に関わらず規制の対象となっています。飛行前の計画でこれらの飛行の方法に該当するかどうかをかならず検討し、必要な場合はライセンスや許可を取得してドローンを飛ばすようにしましょう。
この記事では特定飛行となる「飛行の方法」についてお伝えしてきました。「空域」については『特定飛行とはなんですか – 規制の対象となる空域』をご覧ください。